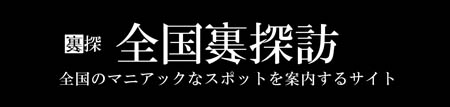全国裏探訪取材班は、長崎県東彼杵郡川棚町にきている。ここには旧日本海軍が兵器製造工場で作られた魚雷の発射試験した試験場「片島魚雷発射試験場跡」があると聞き、現地に足を踏み入れた。

長崎と言えば昔から軍事施設が多い地域で有名である。これにはきちんとした理由がある。湾の水深が深く、島や半島などが中が見えないようにまるで天然の要塞のようになっているため、造船をはじめ、監視所や秘密基地などさまざまな施設が今でも存在している。

また長崎は中国大陸から近いこともあり、本土から攻めてきた時には防衛の要としも軍港としても非常に有用な場所である。それは今でもそんなに変わりはしない。今回の場所は「大村湾」にひっそりとたたずむ軍事施設である。

ここが「片島魚雷発射試験場」である。本当の正式名称は「探信機領収試験場」だ。現在となっては市民の憩いの場として開放されており、連日子連れの家族が多く訪れる癒やしスポットのようだ。

現在では「片島公園」と言われている。この片島という名前はそもそも、日本軍が軍事施設として利用する前までは立派な島となっていた。だが、ここ大村湾の波の穏やかさ、またある程度の距離が確保でき視界も十分確保できることから、1942年に海軍が埋め立てて現在の陸続きの島へと変わった。


ともかく魚雷発射試験場は何なのかと読者の方も首を傾げる部分があると思うが、ここでは佐世保ないし、川棚の海軍工場で新規製造された魚雷もしくは修理した魚雷を納品する前に性能試験の発射(これを領収発射という)を行っていた。無論納品前ということもあり、極秘施設であったことは言うまでもない。

ここで合格した魚雷は「佐世保鎮守府」つまり海軍の施設に納められていたそうだ。では一つずつ見ていきましょうか。

まず入って目につくのは「魚雷発射場」である。カタカナの「コ」の字になっているのにはわけがある。
この先端の塔から魚雷を発射し試験するのだが、先端までは運搬台車に載せられセットされる。そのため、ここにはきちんとレールを敷いた跡が今でも残っている。それはそうだ、最大で約3トン近い魚雷を今みたいにクレーン車みたいなもので簡単に運搬できないだろうし、仮にできたとしても効率とコストと安全性や秘匿性が明らか悪い。

レーンはそのまま真ん中を通り海中へ投下され、発射された。ちなみに発射方向は大村湾の南から長崎市方向へ距離が長くとれるようにしている。

実験とは言え、危険物には変わりないだろうからそのままドボンと落としていたのだろうか。

恐らく当時はこちら側にも何かしらの小屋があったと思われる。しかし内側がレンガ作りとはお洒落である。さすが当時の海軍は英国の影響を受けてるのか。1918年(大正7年)8月竣工らしい。

この建物もレンガ作りが見えている。発射の際木で隠れてしまっているが、画面後ろの頂上に観測所があり、そこから電話連絡をもらい、発射をここからしたようだ。

1945年(昭和20年)頃には観測所から指示ボタンでこちらに発射指示を出すことができたらしい。ちなみに魚雷発射時は水深3メートルまで沈めた。魚雷の背にある発動挺と呼ばれるレバーを倒して、動力機関を始動させると発射する。

約80年前水平線に進んでいった魚雷を見て彼らは何を想い、何を願いどういう未来を描いただろうか。
次回も見て行こう。
#DQN #これはすごい #ズタボロ #マニアック #レトロ #廃墟 #廃村 #廃線 #放置プレイ #歴史 #特殊建築 #観光地 #軍事
(2021)