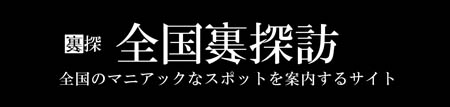全国裏探訪取材班は前回、青函トンネルの建設に新たに導入された技術などを体験コーナーの写真を交え紹介して来た。 そして、取材班はケーブルカーへ乗車。やっと地上までやって来た。
 「世界一の体験ゾーン 歓迎 青函トンネル竜飛斜坑鉄道」開通して大方30年の風雪による劣化だろうか、コンクリートもところどころ傷んでいる。
「世界一の体験ゾーン 歓迎 青函トンネル竜飛斜坑鉄道」開通して大方30年の風雪による劣化だろうか、コンクリートもところどころ傷んでいる。 龍飛崎より北海道を望む。奥の建物上にうっすらと北海道が見えると思う。この海峡の海面下240mを青函トンネルは走る。
龍飛崎より北海道を望む。奥の建物上にうっすらと北海道が見えると思う。この海峡の海面下240mを青函トンネルは走る。 「竜飛崎展望台」から北側のパノラマ写真。
「竜飛崎展望台」から北側のパノラマ写真。竜飛崎は、中世より北前船の寄港地“三厩”とほぼ同じ場世に位置し、少しの栄を見せた。
明治に入り、日清戦争日露戦争と続き、ロシアを仮想敵国とした大日本帝国はこの地に、1901年(明治34年)“龍飛望楼”を設置。さらに1937年(昭和12年)に津軽要塞として砲台を建設。以後は仮想敵国がアメリカに代わり、1940年(昭和15年)に帝国海軍が龍飛特設望楼を設置。敗戦後役目を終えた。
 「龍飛特設望楼」(見張所)それなりに立派だが、今は残念ながら撤去されてしまったようだ。
「龍飛特設望楼」(見張所)それなりに立派だが、今は残念ながら撤去されてしまったようだ。 「青函トンネル本州方基地龍飛」との案内板が建つ。戦後役目を終えたかに見えたが、また、陽の目を見ることになる。当時何もなかったこの地に、1953年(昭和28年)鉄道敷設法別表に三厩―吉岡間の鉄道(のちの海峡線)が追加。そこから建設が始まったのは前回【(4)】で記載したとおりだ。工事が始まったが、まともな幹線道路もなかった建設当初は、まず青森から幹線道路をここまで引っ張るところからのスタートだった。往時はここにたくさんの工事関係者の施設やショッピングセンター、作業寮、家族用アパート、学校などが立ち並んでいた。
「青函トンネル本州方基地龍飛」との案内板が建つ。戦後役目を終えたかに見えたが、また、陽の目を見ることになる。当時何もなかったこの地に、1953年(昭和28年)鉄道敷設法別表に三厩―吉岡間の鉄道(のちの海峡線)が追加。そこから建設が始まったのは前回【(4)】で記載したとおりだ。工事が始まったが、まともな幹線道路もなかった建設当初は、まず青森から幹線道路をここまで引っ張るところからのスタートだった。往時はここにたくさんの工事関係者の施設やショッピングセンター、作業寮、家族用アパート、学校などが立ち並んでいた。 竜飛崎展望台から下写真の赤丸地点から矢印方面、南東方面を見る。今は建物はそれほどない。ただ1988年(昭和63年)の青函トンネル供用開始が始まり、保守のみの扱いとなったため、また大勢の人間が去っていった。まさに栄枯盛衰と言ったところか・・
竜飛崎展望台から下写真の赤丸地点から矢印方面、南東方面を見る。今は建物はそれほどない。ただ1988年(昭和63年)の青函トンネル供用開始が始まり、保守のみの扱いとなったため、また大勢の人間が去っていった。まさに栄枯盛衰と言ったところか・・ (出典 国土地理院より 1975年撮影)
(出典 国土地理院より 1975年撮影)起工式は1971年あたりから、この龍飛崎の高台に工事基地が設けらた。国土地理院の1975年の航空写真では青函トンネル建設のための多くの施設が立ち並んでいるのが分かる。この工区だけでも鉄道建設公団関係者約400人、請負企業関係約800人がこの坑口から従事していた。そして、青函トンネル全体の工事従事者は延べ1389万人に達した。
 「青函トンネル記念館」の中には様々な展示がされている。現在竜飛海底駅(現竜飛定点)は新幹線の施設となっているため、一般人が行くことはできないが、この地上の“青函トンネル記念館”からケーブルカーへ乗車して海面下140mへ探検する“体験ツアー”プランがあるようだ。
「青函トンネル記念館」の中には様々な展示がされている。現在竜飛海底駅(現竜飛定点)は新幹線の施設となっているため、一般人が行くことはできないが、この地上の“青函トンネル記念館”からケーブルカーへ乗車して海面下140mへ探検する“体験ツアー”プランがあるようだ。次回はいよいよ最終回。再度竜飛海底駅から列車で帰路につく。
#外ヶ浜町 #木古内町 #鉄道 #これはすごい #マニアック #巨大建築
(2012)